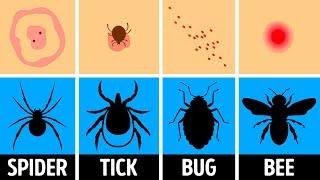Published On Jan 27, 2023
『かぶとむし』その禍根は、深く、太く、強く刻まれてるんですねぇ
明日使えない無駄知識を、あなたに
圧縮雑学チャンネルです
このチャンネルでは、どうにも微妙な無駄知識を、
短時間で詰め込むという動画作成を目指しております。
作者の都合上、更新は不定期となります。
その分、フフッと笑えるような動画を作りますので、
よろしければ応援お願いします。
仕様楽曲製作者様サイト
https://roundloudness.localinfo.jp/
補足
カブトムシとオオスズメバチ
オオスズメバチの活動時間は、おおよそ日中
その為、オオスズメバチに勝てないカブトムシは
夜行性として、比較的安全な時間を選んだのかもしれません。
本来、甲虫の硬い外骨格にはオオスズメバチの針は通らず
相性は悪かったわけですが
どういう訳か、大体のオオスズメバチは、カブトムシの弱点である
足先を狙う術を身に着けています。
山口大学の調査によると、蜂除けスプレーで蜂を寄せ付けないと、
カブトムシは正午ごろまで樹液にかぶりついていたそうで
攻撃を受けなければ日中の活動もできる可能性が示されました。
小学生の研究
カブトムシの研究をしていたのは、当時小学6年生の柴田亮さん
自宅に植えてあるシマネトリコの木には、日中もカブトムシが
飛来することに疑問を持ち、研究を始めました。
山口大学理学部のアドバイスも受け、主体的に研究に取り組んだ結果
米国の生態学専門誌『エコロジー』にその成果が掲載される
快挙となりました。
純粋な探求心は、時として年齢に関係なく結果をもたらすんですね。
因みに、山口大学には亮さん本人からコンタクトを取っております。
行動力がすごい。
樹皮の厚い木に群がる理由
カブトムシやクワガタ虫は、クヌギの木と言った樹皮の分厚い木の
樹液に群がる傾向があります。
実は、これにはある理由があるんです。
そもそも樹液と言うのは、樹皮のすぐ内側を通る師部と言う組織を通り、
光合成による生産物などを樹全体に送る血液の様な役割をしています。
この師部と言う組織は、糖も運んでいるため、樹液は基本的に
甘くなります。
しかし、糖を運ぶうえで、病原菌や害虫がネックとなります。
それらからから身を守るために、樹液にはポリフェノールが含まれているそうです。
このポリフェノールの主成分は『タンニン』であり
高い抗菌作用と、強い渋みを持ちます。
一般的な樹皮の薄い樹木は、このタンニンにより樹液に渋みを持たせ
身を守っています。
反対に、クヌギ等の樹皮の分厚い樹木は、多くは樹皮自体に
タンニンを含んでいます。
その為、樹液にタンニンを含ませる必要がなく、樹液が
甘いままの状態になります
つまり、昆虫たちは渋みを感知し、より甘くておいしい蜜に
集まっているわけです
因みに、そもそも何で樹液が漏れるかと言うと
大概は虫による食害で傷がついて、漏れ出します。
代表的なところで、カシノナガキクイムシや、カミキリムシ
ボクトウガの幼虫などが居ます。
特に、ボクトウガの幼虫は、傷つけた樹液に集まる小さな虫を食べるそうで
わざと木に傷をつけるそうですよ。
面白いもんです。
#雑学
#無駄知識
#昆虫
#カブトムシ
#オオスズメバチ
#科学